山口行治(やまぐち・ゆきはる)

株式会社ふぇの代表取締役。独自に考案した機械学習法、フェノラーニング®のビジネス展開を模索している。元ファイザージャパン・臨床開発部門バイオメトリクス部長、Pfizer Global R&D, Clinical Technologies, Director。ダイセル化学工業株式会社、呉羽化学工業株式会社の研究開発部門で勤務。ロンドン大学St.George’s Hospital Medical SchoolでPh.D取得(薬理学)。東京大学教養学部基礎科学科卒業。中学時代から西洋哲学と現代美術にはまり、テニス部の活動を楽しんだ。冒険的なエッジを好むけれども、居心地の良いニッチの発見もそれなりに得意とする。趣味は農作業。日本科学技術ジャーナリスト会議会員。
◆スポーツをAIと楽しむ
なぜ人工知能(AI)が大きな話題になるのか。ビジネスの生産性が向上するポジティブな経済効果だけではなく、社会全体の組織や制度に大きな影響を与える可能性、特に、多くの人びとにとってネガティブな影響があるかもしれないという、リスク意識が潜在的にあるのだろう。多分、多くに人びとのリスク意識は、因果関係が説明できなくても、的を得ている。
「AIのゴッドファーザー」として尊敬されている、ノーベル賞受賞者のジェフリー・ヒントン博士はAIが人類を支配する危険性を具体的に提示して、人類を守るAIマザーを提案している(https://news.yahoo.co.jp/articles/f99a52260f6041a4d190e23fc35d4a5b83586563?page=1 )。筆者のように、植物好きであれば、AIマザーツリーのほうが居心地が良い。戦争と殺りくを繰り返す「人間中心」の価値観は安心できない。そうは言っても、巨額の開発投資がからんでいるAI開発では、現状で科学の理解が及ばないマザーツリーを開発する冒険はできない。人間が投資をするのだから、人間が理解できる「人間中心」の物語を模索するしかないだろう。
人間は、鋭い牙(きば)や角(つの)は無いけれども、集団行動が得意で、とても残虐な動物だ。人間の過度な暴力性を緩和するために、祭りやスポーツが役立っていると思われる。現在のAI技術は、勝敗の基準が明確な、ゲームやコンテストを得意としている。勝敗というよりは、出来栄えや技といった、より主観的な「アート」の世界でも、生成AIは素人以上の作品を作り出している。高速ビデオの画像解析などのセンシング技術の進歩によって、AIはスポーツ選手のコーチ役として、場合によっては審判役として、有用なレベルになっている。しかし、スポーツの観客の一員として、スポーツをAIとともに楽しむことはできるのだろうか。
AIがスポーツ競技の解説者として、実況中継をすることはできそうだ。スポーツを楽しむためには、勝敗の確率だけではなく、それぞれの競技者の立場から、競技の展開を読み解くこと、水面下での駆け引きを理解することが不可欠で、場合によっては、試合が始まる以前の取材が重要になる。AIを「スポーツを楽しむ」目的でトレーニングすれば、素晴らしいAI解説者になるかもしれない。
勝敗の確率は「人間中心」ではあっても、それぞれの競技者が中心ではない。筆者は個体差が重要なデータの機械学習法、フェノラーニング®を考案して、そのビジネス応用を模索している。個体差を理解するためには、その個体差は何を表現しているのか、そして、それぞれの個体が中心となるような表現空間(データモデル)を、いかに構成するのかという、相互に関連する難問を個別の問題ごとに考えて、局所的なデータモデルを接続する工夫が重要だ。「スポーツを楽しむ」ことは、スポーツの競技ごとに考えて、接続する。オリンピックのような、金メダルの個数によって競技を接続するのは、国家中心であっても人間中心とは言えない。AI解説者とともに、工夫する余地はありそうだ。
スポーツは、直接的には役立たないことが特徴らしい。医学は、もちろん直接的に役立っている。しかし、認知症の治療のように、現在の医学の限界を越えようとするときに、スポーツのような、人間的なパフォーマンスが計測しやすい競技を使って、AI技術の進歩を取り入れながら、試行錯誤することは有益だろう。
スポーツ実況解説AIは、AIマザーに向かう道の、最初の一歩になりそうな気がしている。

〇 Lovable実況中継-3 二拠点生活を楽しむAIを使ってDIY
今回は、「楽しく学ぶ二拠点生活-AIを使ってDIY」という、ホームページを作ってみよう。問い合わせフォームは用意するけれども、ログインが不要な公開サイトだ。将来的には、ログインしたユーザーは、APIキーを共有して、GoogleマップなどのWebアプリを操作できるようにする。当初は、別途作成したマップなどの記事を、キーワードをつけて整理できるようにする。ブログのように、記事を追加してゆくだけの機能を実装する。
以下の『』がLovableに与えるプロンプトです。
『Webアプリを作ってください。nestnasu.netというURLで公開予定です。Webアプリの名称は「楽しく学ぶ二拠点生活-AIを使ってDIY」です。「ネストNASU」というNPO法人が管理します。管理人は1人です。このWebアプリは、NPO法人ネストNASUのホームページで、管理人がブログのように、毎週1回程度、記事を追加します。記事には、あらかじめ設定したキーワードをつけます。読者がキーワードを選択して、新着順に表示します。記事には、キーワードのテーマごとに、AIの便利な使い方を記載します。
<設計概要>
NPO法人ネストNASUのホームページで、名称は「楽しく学ぶ二拠点生活-AIを使ってDIY 」です。1人の管理人が、ブログのように週1回程度記事を投稿します。
<実装する機能>
記事につけるキーワードの管理。キーワードは、那須の地図、日曜大工、週末農夫、那須の郷土料理、湯治、DIYショップ、です。記事には、複数のキーワードをつけることも可能です。キーワードは追加できるようにします。
読者がキーワードを選択して記事を表示します。キーワードではなく、新着記事を選択することもできます。記事には読者が「花マル」をつけることができます。
NPO法人の概要を表示するWebページを作ります。
読者が問い合わせをできるように、Webフォームを作ります。問い合わせフォームは、用件、氏名(ニックネームも可)、返信用のメールアドレス、問い合わせ内容、です。
記事を投稿するためのWebフォームも作ってください。投稿フォームは、タイトル、投稿者名、キーワードのチェックリスト、AIソフト名、記事内容、です。記事は、HTMLで作成し、画像も含みます。記事を投稿した日時をタイムスタンプしてください。
<デザインコンセプト>
自然豊かなカントリーサイドの印象の緑系グラデーション配色
理解しやすくて、パソコンでもスマホでも読みやすい、ブログ風のユーザーインターフェース』
Lovableにもだいぶ慣れてきて、詳細な指示を与えたので、上図のWebサプリ作成に10分ほどかかった。週末農夫を菜園と解釈するなど、追加されたメッセージもかなり洒落(しゃれ)ている。Suprabaseとの接続は比較的簡単だったけれども、詳細はチェックできていない。デザインはシンプルなので、多少、那須らしい写真など配置してゆきたい。「AIを使ってDIY」という内容は、このホームページをLovableでAIを使ってDIYしているという劇中劇でもある。次回は、デザインをAIを使ってDIYしてみたい。
◆閑話コラム記事16 個体差の技術哲学(2)
個体差とは何かということを、人類で最初に深く考えた哲学者は、近代哲学の巨人、ゴットフリート・ライプニッツ(1646~1716年)だ。そして、個体は「モナド」で構成されるという、哲学的としか言いようのない難解な議論を後世に残した。モナドは素粒子のようなものなので、見かけ上は個体差が無い。光に個体差が無いのは本当に不思議な現象で、個別の光子であっても、波動として干渉する場合は、存在する場所が異なっても、同じ光子のように振る舞う。ライプニッツの時代には、素粒子の存在すら哲学でしかなかった。西欧の一神教の神には、個体差がない。モナドは、神にしか見えない個体なのだろう。
筆者のように、神の視野を持たない俗人にとって、モナドにも個体差があるように思われる。モナドは容姿しかわからないので、別の場所から見た別のモナドは異なって見えるのではないかと疑っている。モナドの見かけ上の個体差を問うことが技術の問題であって、個体とは何か、個体はどのように形成されるのかという、哲学的な個体論は、技術の問題を解決した後に議論すほうが良いと考えている。哲学は概念を問題にするけれども、技術はデータによって進歩する。プラグマティズムの教えに従って、概念を明確にするためには、概念を使った場合の効果をデータによって明確にする作戦が、個体差の技術哲学だ。
筆者の考える技術哲学は、技術について哲学的に考えることではなく、哲学的な概念を、データによって明確にするための技術だ。理論よりも測定を優先する実験主義でもある。見たことも無いものを考えることはできない。神は信じることしかできない。データも、信用できるデータであることが最優先で、データを信じることから始まる。
今回は、個体差の技術哲学について、哲学的に考えてみた。新しい哲学が社会制度を超克する、全く新しいイメージで塗り替える、可能性があるのであれば、それは精神医学だと思われる。筆者は、1980年代に、日本と英国の臨床研究の現場において、米国流の国際疾病/医療行為分類ICD9-CMを導入する仕事に関与したことがある。精神医学が、米国流に大転換した時代だ。その最大の貢献は、新規な向精神薬の開発を促進したことで、精神医学を薬物療法が「不治の病」のイメージから脱却させた。
米国も21世紀になって、薬物療法の先進国というよりも、違法ドラッグが蔓延(まんえん)して、精神科医が大儲(もう)けをする、世界でも異常な精神医学の国家となっている。従軍経験者では、大量の精神異常が発病している。離婚訴訟にも精神医学が関与する。単純に言えば、新しい精神疾患が蔓延しているのに、新しい向精神薬の開発が停滞してしまった。
次回は、個体差の技術哲学が、哲学的に、現在の米国流精神医学を超克する可能性について考えてみたい。
◆閑話コラム記事17 コンテンツ作り大国
中長期的な経済政策として、現時点で真剣に研究する価値があるのは中国経済だろう。米国経済は直近の課題として最重要であっても、中長期的な経済政策としては学習済みだ。筆者は経済政策の専門家ではないし、経済学の素養も無いけれども、中国経済が、モノ作り大国として世界レベルで成功して、国内市場では、ロボットとAIを活用するサービス作りに躍進している。中国全体では、政治や社会の問題が山積みであっても、世界をリードする経済大国として、独裁的な国家資本主義体制によって、中長期的な経済政策を着実に実施している。
一方で、中国経済の弱点は、過度に米国経済との対立軸を重視していることだと思われる。米国経済との競争に勝利できたとしても、米国経済が本当に行き詰ったときは、中国経済の終わりの始まりだ。筆者も国民の一人として、日本が、政治や社会において、米国や中国よりも安定していることに責任を持ちたい。国際的にも、日本の安定した政治や社会がリスペクトされ、中国経済の経済政策を批判的に研究して、世界レベルで成功する経済大国に復活することを期待したい。
AI技術を活用することで、モノ作り、サービス作りにおいて、競争優位性があることは想像しやすい。しかし、その競争は、国家間だけではなく、国内の雇用との競合でもある。一方で、AI技術は、コンテンツ作りの現場を一新するだろう。アート、デザイン、ゲーム、コンテストに加えて、スポーツのコンテンツもAIとともに作る時代になる。コンテンツの核心は、表現の思想性であって、鑑賞者とともに作っていくことになる。鑑賞AIが鑑賞者(人間)の数を越えない限り、AIと人間が競合することは無いだろう。
--------------------------------------
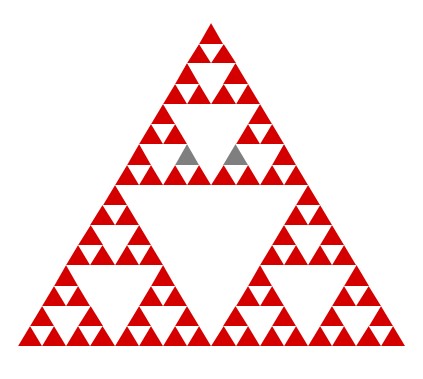
『みんなで機械学習』は中小企業のビジネスに役立つデータ解析を、みんなと学習します。技術的な内容は、「ニュース屋台村」にはコメントしないでください。「株式会社ふぇの」で、フェノラーニング®を実装する試みを開始しました。











コメントを残す