山口行治(やまぐち・ゆきはる)

株式会社ふぇの代表取締役。独自に考案した機械学習法、フェノラーニング®のビジネス展開を模索している。元ファイザージャパン・臨床開発部門バイオメトリクス部長、Pfizer Global R&D, Clinical Technologies, Director。ダイセル化学工業株式会社、呉羽化学工業株式会社の研究開発部門で勤務。ロンドン大学St.George’s Hospital Medical SchoolでPh.D取得(薬理学)。東京大学教養学部基礎科学科卒業。中学時代から西洋哲学と現代美術にはまり、テニス部の活動を楽しんだ。冒険的なエッジを好むけれども、居心地の良いニッチの発見もそれなりに得意とする。趣味は農作業。日本科学技術ジャーナリスト会議会員。
◆個体差の位相
主体性のある個人だけではなく、会社や国家のような集団においても、個性や個体差はある。個体は、自他を区別するというよりも、個体の内側と外側を区別する仕組みに思える。その意味で、個体差にとって最重要なのは、個体の境界となる場所だ。個人の個体差では、性別や年齢そして肌の色など、外見が重要視される。集団の場合は、大きさが重要視される。
個体の外見は、誰がどこから見ているのかということで、解釈が大きく変化する。多分、中世では神の視点から、近代では抽象的で普遍的な「人間」の視点から見ていたのだろう。個体の境界の近くにいる他者からの視点は、生活者の視点となる。集団も、地域の視点が重要だ。
個体差の評価には、誰がどのような視点で評価しているのかが問われる。個体と個体の差異である個体差をデータにすると、単なる数字になってしまう。個体差のデータにはバラツキがあって、確率分布関数で表現されるとしても、もともとの個体の場所の差異の情報は失われる。
視覚や聴覚の場合、個体の場所の情報は、画像や音の「場所」における位相差として検出される。音の位相差は、音色であり残響音となる。画像の位相はエッジ(境界線)として検出され、視線の方向性(パースペクティブ)の情報を与える。音や画像の位相は、データを周波数分析(フーリエ変換)するときに明確になり、通常は、パワースペクトラムとして、実数値で表示される。しかし、位相そのものは、フーリエ変換において複素数として表現されていて、実数化するときに、位相の情報は失われる。複素数としての位相は、数学的なイメージなので、個体差の位相も、複素数で表現されるのだろうと「想像」している。
集団の個体差は、集団の境界の近くで、位相を持つ複素数として表現されるのだろう。自然の集団、例えば森やシマウマの群れの境界は、なんとなくわかるようで、明確に定義しようとすると難しくなる。国境は明確に定義されているようだけれども、合意の無い場合も多い。それでも国境が複素数であれば、なんとか表現できるかもしれない。
抽象的な文章になってしまったけれども、フェノラーニング®において、個体差を機械学習する基本的な考え方をまとめている。複素数としての「個体差の位相」は実装できていないけれども、全ての個体が中心となるような、高次元の球体の位相を、データ行列として表現する場合に、とても「疎」(スパース)な関係行列となることまでは、アルゴリズムとして実装できている。多分、関係行列の固有値を計算すると、実数値ではない固有値が混ざっていて、何らかの意味を持っていると「想像」している。
個体差に関連するデータの、「データ行列」の意味を探索する仕事に、機械学習技術が役立つだろうという発想がフェノラーニング®の出発点だった。「個体差は、個体差の表現の個体差である」という哲学的仮説の周辺を、何度廻(まわ)っただろうか。個体差に関連するデータを収集して、その意味を探索する実務を始めたいものだ。前稿ではスポーツ実況中継に言及した。筆者はスポーツにあまり縁がないので、家庭菜園をDIYするためのデータを考えることにしよう。

〇 Canva実況中継-1 お絵描きDIY
今回は、Canvaという生成AI(人工知能)が組み込まれたデザインツールを使ってみた。10行ほどの情景描写をプロンプトで与えて、生成されたスケッチを多少修正した(上図)。アジア人の描画は苦手なようで、日本人とか、もっと具体的に指示するほうがよさそうだ。ロボットと宇宙船はレパートリーが多くて、毎回違う描画になる。ロボットが料理を手伝っているはずなのだけれども、机の上にいるのが精いっぱいのようだ。
仕事では無料のAIツールを使わないようにしている。現在、仕事に使っているのはGeminiとLovableの2つだけだ。今回は無料のCanvaを使った。Geminiでもお絵描きはできるし、生成AIとしての出来栄えもCanvaよりは上等かもしれない。しかし、Geminiでは動画も生成できるし、音楽もできる。GeminiをChatGPTのような使い方をすると、なんでも上手にこなすので、依存症になりそうだ。
生成AIの依存症にならない一つの方法は、使用目的に合わせて、ツールを使い分けることだろう。CanvaはAI機能よりも、デザイン機能のほうが充実しているので、お絵描きDIYには適している。実際に使ってみて、月額サブスク料金は払ってもよいかと思うし、NPO法人の場合は、無料で使えることもうれしい。
劇中劇のイメージをGeminiで描いてみた2か月前のお絵描きが下図だ。

AIを使ってプレゼンテーションを作成する方法をプレゼンしている。今回は、人工的な自然環境の中で、宇宙船を眺めながら調理している情景を描いてみたつもりだけれども、劇中劇にはなっていない。しかし、AIツールを使ってDIYすること自体が劇中劇なので、1年後には、もう少しピントが合った、劇中劇のスケッチを描けるようになるだろう。高齢者がAIツールを楽しく使って、しかも依存症にはならないで、多少なりとも社会の役に立つ、そんなシナリオを、AIツールの実況中継で模索している。
◆閑話コラム記事18 個体差の技術哲学(3)行動変容
個体差の技術哲学が、哲学的に、現在の米国流精神医学を超克する可能性について考えている。行動経済学の考え方を、精神医学に応用してみようという、安易な発想だった。しかし、行動経済学における行動は、不合理ではあっても「正常」な心理学的状態において、無害な経済行動に限定している。精神医学のような、「異常」で、場合によっては犯罪的な行動の場合は、慎重に再考する必要があることがわかってきた。
個体差の技術哲学の出発点は、ゴットフリート・ライプニッツ(1646~1716年)の『モナドロジー』(岩波文庫 青 616-1)だ。ライプニッツは人類最初のスピノザ主義者であったという拙稿の勝手読み『みんなで機械学習』第20回「機械学習の学習」(https://www.newsyataimura.com/yamaguchi-90/ )について、「モナドロジー」を丁寧に再読することから始めている。
スピノザの「エチカ」は、本連載でも幾度となく言及している。スピノザが議論した、「自由」による行動変容の射程は広大なので、精神医学的な状況においても、行動変容の指針となるだろう。「モナドロジー」を読み込む作業は、本連載を始めた2017年からの宿題で、急ぐ必要はないけれども、残り時間は少なくなってきた。
◆閑話コラム記事19 島国の中に島国を作る―島国特区
劇中劇という表現形式が、機械学習技術を革新することは、以前の拙稿『みんなで機械学習』第58回「データ化学の沃野」(https://www.newsyataimura.com/yamaguchi-140/ )から時々言及してきた。日本の近未来を、劇中劇してみたい。日本が島国であるという特徴を生かして、島国の中に島国を作る、島国特区について考えてみる。
産業革命を生んだ英国は、典型的な島国だ。世界の国々を植民地支配した帝国主義時代もあったけれども、現在は島国に戻っている。最近でも、研究開発は盛んで、世界のAI技術や新薬開発をリードしている。しかし、英国のイノベーションの事業化は、ほとんどが米国企業だ。知財権が英国に支払われていても、雇用環境などの英国経済には、ほとんど寄与していない。世界の経済は、大陸の覇権国家が支配していて、軍事経済の色彩が強い。
日本も島国だ。日本の産業構造は老朽化して、特に地方の人口減少と産業衰退が著しい。政府としては、地域おこしの政策を工夫して、財源を地方に配分しているけれども、成果は乏しい。地域おこしの政策に、劇中劇の表現形式を導入して、東京都の伊豆七島など、各自治体の離島を「島国特区」として、地域おこしの政策提案を募ってみてはどうだろうか。
離島から、近未来のデータ文明の、新しい社会インフラと革新的ビジネスが生まれることを期待したい。筆者はスマート・テロワール(注、『スマート・テロワール 農村消滅論からの大転換』〈松尾雅彦、浅川芳裕、他著、学芸出版社、2014年〉)に好感を持っているけれども、スマート・テロワールは、大陸の田園風景が原風景になっている。
山が多く島国の日本では、北海道や平野部の風土にしか適合しないのが難点だ。スマート・テロワールの思想を、島国の原風景において、未来志向の情報処理技術とともに、コンパクトに劇中劇化してみたい。離島という、少子高齢化社会の最先端地域で、DIYを楽しむ社会実験の、独立性の高いデータを集積する試みだ。島国において、新しい社会インフラと革新的ビジネスをシミュレーション(模擬実験)するための「データ」となるだろう。
(注)スマート・テロワール=「スマート」と、フランス語の「テロワール」(作物を作る土地の気候条件や風土)とを掛け合わせた造語。農と食を地域の中で循環させ、持続可能な食料自給を目指す取り組み。カルビーの創業者・故松尾雅彦氏が著わした『スマート・テロワール 農村消滅論からの大転換』で提唱した。
--------------------------------------
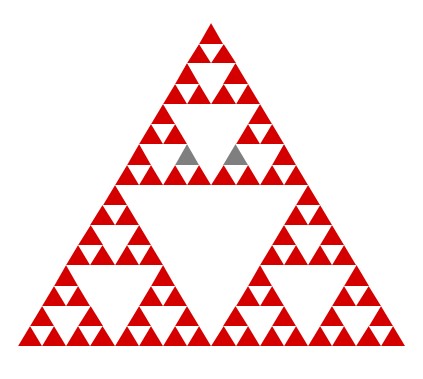
『みんなで機械学習』は中小企業のビジネスに役立つデータ解析を、みんなと学習します。技術的な内容は、「ニュース屋台村」にはコメントしないでください。「株式会社ふぇの」で、フェノラーニング®を実装する試みを開始しました。











コメントを残す