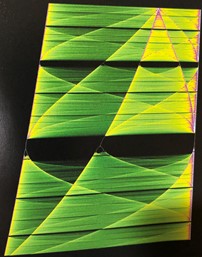山本謙三(やまもと・けんぞう)
 オフィス金融経済イニシアティブ代表。前NTTデータ経営研究所取締役会長、元日本銀行理事。日本銀行では、金融政策、金融市場などを担当したのち、2008年から4年間、金融システム、決済の担当理事として、リーマン・ショック、欧州債務危機、東日本大震災への対応に当たる。
オフィス金融経済イニシアティブ代表。前NTTデータ経営研究所取締役会長、元日本銀行理事。日本銀行では、金融政策、金融市場などを担当したのち、2008年から4年間、金融システム、決済の担当理事として、リーマン・ショック、欧州債務危機、東日本大震災への対応に当たる。
異次元緩和の開始から7年半、マイナス金利の導入から5年弱、YCC(イールド・カーブ・コントロール)の実施から4年が過ぎた。銀行はいよいよ苦境に立たされている。
考えてみれば、当たり前だ。預金金利はゼロ%に張り付く。一方、リスク・フリー・レートである国債(10年以下)の市場利回りは、5年近くゼロ近傍にある。負債と資産の金利が同一水準(ゼロ%)であれば、収益をあげるどころか、経費も賄えない。 記事全文>>

 バンコック銀行執行副頭取。1977年東海銀行入行。2003年より現職。米国在住10年。バンコク在住22年。趣味:クラシック歌唱、サックス・フルート演奏。
バンコック銀行執行副頭取。1977年東海銀行入行。2003年より現職。米国在住10年。バンコク在住22年。趣味:クラシック歌唱、サックス・フルート演奏。